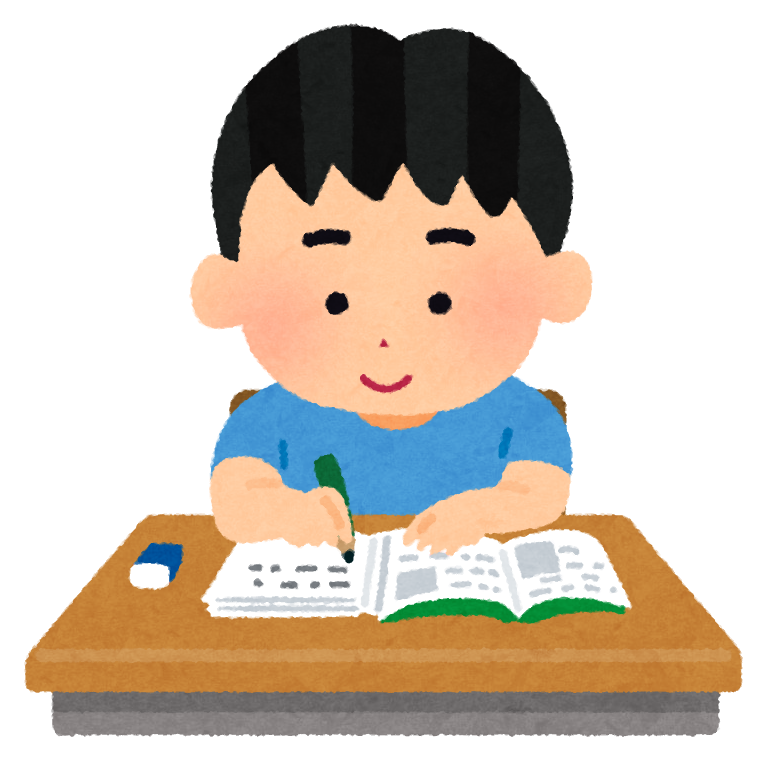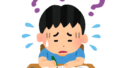宿題ってなんのためにあるのでしょう。宿題をすると頭が良くなるのでしょうか。
今日はそんなことについて考えてみたいと思います。
宿題は「勉強」を「学習」に変える
基本的に宿題は出されるものです。出された以上、例え嫌でもやらなければなりません。
「小学校で習ったことなど、大人になったらどうせ役に立たないから」などの理由でやらないことは認められません。
その意味では、宿題はやらされる勉強であって、主体的な学びではありません。
yamaが子どもたちに、「宿題だけしてても頭は良くならないぞ~。早くやっつけてしまおう。やっつけて早く遊ぼう。」などと言うのはそのためです。自分から進んで主体的に学ばなければ、けして身にはつきませんし、頭も良くはならないのです。
「やらされる勉強」から「主体的な学び」へ
宿題の内容を見てみると、漢字の書き取りや計算などの反復練習が多いです。いわゆる「詰め込み」とも捉えられる内容がほとんどです。子どもにもよるでしょうが、けして「楽しい勉強」ばかりではありません。「勉強は楽しくあるべき」ではなかったのでしょうか。
やりたくなくても“やってみる”ことに大きな意味があるのです。
「宿題=意味がない」ではありません!
「なぜこの宿題をするの?」と子どもが感じることは自然です。でも、宿題にはちゃんと目的や理由があります。
たとえば…
計算練習 → 数に慣れる力、スピードの土台づくり
音読 → 言葉の感覚を育てる力、記憶力や理解力の基礎
日記や感想文 → 考える力、表現する力
宿題には「土台」をつくる役割があります。すぐに役立つわけではないかもしれませんが、コツコツ続けることが力になります。
宿題の本当のねらいは「習慣化」
宿題は、その内容以上に「毎日続けること」が最大の目的です。
毎日机に向かう
時間を管理する
やる気がない日でも取り組む
これらの経験を積み重ねることで、やがて子どもは「自分から学ぶ力」を育てていきます。
外から「やらされる勉強」が、自分から「やりたい学び」へと変わっていくのです。
宿題は「楽しく」なくても大丈夫
「勉強=楽しくなければならない」と思う必要はありません。
たしかに、楽しめる工夫も大切ですが、「大変なことに挑戦して乗り越える」経験が、子どもの心を育てます。
スポーツや楽器の練習と同じように、最初は大変でも、続けるうちに「できた!」「自分にもできるかも」という気持ちが育ちます。
ご家庭でのちょっとした支援が、大きな支えになります
保護者の皆さんにお願いしたいのは、「結果」より「過程」を認めてあげることです。間違ってたって、うまくできてなくたって、いいんです。大切なのは、「できた!」「やりきった!」という子どもの気持ちに寄り添い、一緒に喜んであげることです。
「よく机に向かったね」
「最後までやりきったね」
「毎日がんばってるね」
「大変だったけど終わったら嬉しいね」
これらの声かけが、「勉強=自分の力で乗り越えられるもの」という自己効力感につながります。
最後に
子どもたちは、「やらされる勉強」からスタートします。でも、毎日続けるうちに、自分なりの「学び」を見つける力を育てていくのです。
宿題は、その第一歩。
どうか子どもたちの日々の小さな努力に、あたたかなまなざしを注いでください。ご家庭でも、無理のない声かけ・支援をお願いします。
わからないことやご相談があれば、いつでもお気軽にスタッフに声をおかけください。